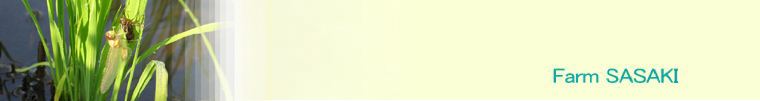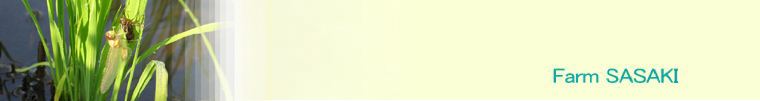|
|
|
| 減農薬のための田の虫図鑑 |
宇根豊
日高一雅
赤松富仁著 |
農家の視点から、田んぼの虫を害虫、益虫、ただの虫に分類した図鑑。宝ダニはちょっとグロテスクですね。 |
| 田んぼの生きものおもしろ図鑑 |
湊 秋作編 |
読み物としても面白いです。この図鑑に載ってない生き物がいるというあたり、田んぼにはホントにたくさんの生き物が住んでいます。 |
| 米ヌカを使いこなす |
農文協編 |
米糠はバランスの良い肥料であるし、抑草にも効果的です。でもみんな玄米食に目覚めたら調達できなくなるなぁ。田植え後の米糠散布はポピュラーですが、そんなことして遮光による抑草を考えるより、田植え前に散布してオタマジャクシやイトミミズを増やした方が効果的かも知れません。 |
| 米ぬかとことん活用読本 |
農文協 |
稲作だけでなく、生活の中で使える米ぬかの活用法を列挙してあります。イトミミズの生態が参考になりました。低温菌→ミジンコ類→イトミミズの循環が大切ですね。要は微生物をいかに増やすかなんです。見えないものを大切にする先人の知恵がある気がします。 |
| 除草剤を使わないイネつくり |
民間稲作研究所編 |
文字通り、除草剤を使わないで稲を作る方法を具体的に紹介している。除草ではなく、抑草という考え方。 |
| あなたにもできるイネの診断 |
農文協編 |
自分のように知識のない人はおろか、毎年の習慣で稲を作っているベテランにも、基本に立ち返るという意味で必須の読本。写真解説が丁寧。 |
| 新しい不耕起イネつくり |
岩澤信夫 |
不耕起栽培の重鎮、岩澤信夫氏による著作。実践書。ラウンドアップによる除草が紹介されているあたり、今の稲作の技術の限界がこのあたりなのだろう。田んぼを一つの小さな生態系として見るのはなかなか難しいと痛感させられる。 |
| 田んぼビオトープ入門 |
養父志乃夫 |
農業を生業としない、いわば趣味の本ともとれるが、本当においしい米ができるのには調和された自然が必要なのである。そういう意味でとても大切な著作である。各季節ごとの生き物たちの紹介がとても参考になる。でも一人で実践するのは無理だなぁ。消費者が、消費者から当事者になって初めて可能かと思います。 |
| 季刊 うかたま |
農文協 |
スローライフをさりげなく提案する季刊誌。内容はさりげないけど冊子づくりには結構気合い入ってます。 |
| おいしいお米の栽培指針 |
農文協 |
おいしいお米の条件として、Mg/K 比が高い方が良いという話。
細かいところまで読み切れてませんが、追肥を誤るとおいしくない米になってしまう。 |
| イラスト図解農業のしくみ |
日本実業出版社 |
「現代農業のしくみ」です。今の一般的な農業がどのようにして行われているか分かります。 |